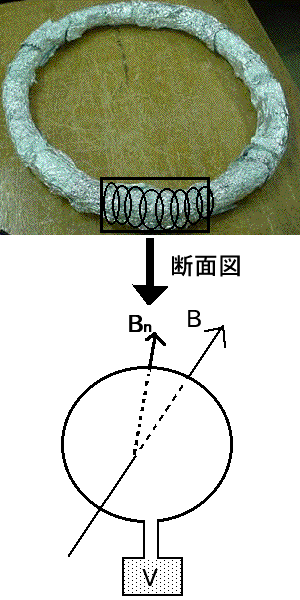
|
【実験の下準備】
「この装置の役割は?」
|

|
この疑問を解決するために、ゴム管にコイルを巻きつけたことによってできた環(わ)のうち、※一つの環に注目して考えてみましょう。
※(以下『コイルA』と呼ぶことにします)
コイルAの面に垂直な磁場成分をBnとします。実験では※交流を扱っているので、時間とともに変位する磁場が生じます。よって、このコイルには誘導起電力Vが現れます。
※そもそもアンペールの法則は定常電流についてのみ成り立つ法則であり、交流電流には本来適用することができません。しかしこの実験では、「準定常電流」と呼ばれる低周波の交流電流を扱っているのでアンペールの法則を体感するにあたって大きな影響を与えません。このことについては後ほど詳しく記述します。
|
|
|