グラム陽性、しょう油乳酸菌Pediococcus halophilusの異化代謝産物抑制
- しょう油は古くなると黒くなる!
- しょう油にはアミノ酸が豊富にある。またいくらかの糖、特にペントースが混じっている。
アミノ酸と糖、特にペントースとは反応して色素を生ずる。そのため色が着くのである。
- しょう油は、しょう油乳酸菌Pediococcus halophilusによる大豆の発酵産物である。そのような
細菌といえども、人間と同様に食べ物に好き嫌いがある。ブドウ糖や果糖などのヘキソースを
一番好む。そのため、キシロース等のペントース類があっても後回しにしてしまい、培地中、つまりは
しょう油の中にペントースを食わずに残してしまう。このような好き嫌いの現象を「ブドウ糖効果」または
「異化代謝産物抑制」(難しい言葉ですね)と呼ぶ。そしてこのような調節機構が働くお陰で、最終的に
「古いしょう油が黒くなる」のです。
- この問題の解決法は?
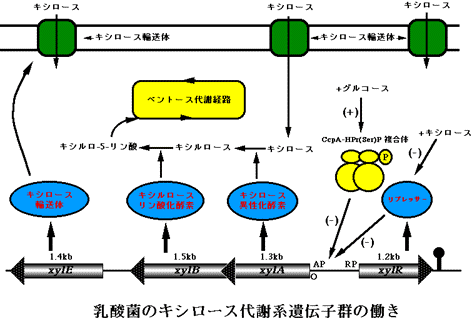 私達はまずこの菌(Pediococcus halophilus)のキシロース利用系酵素の遺伝子群をクローニングしました。
その遺伝子DNAの塩基配列を決定することにより、この遺伝子群の発現制御機構
(異化代謝産物抑制)を推測することができました(図参照)。そこで、この調節に関わる
大事な遺伝子に変異を与えようと考えています。つまり、この異化代謝産物抑制という遺伝子発現制御機構を
壊すことにより、この菌の糖に対する好き嫌いをなくしてやることができるはずです。
すると、キシロース等のペントースもブドウ糖などのヘキソースと同様によく利用するようになり、
しょう油中のペントースを少なくして、黒くなるのを防ぐことができると踏んでいます。
私達はまずこの菌(Pediococcus halophilus)のキシロース利用系酵素の遺伝子群をクローニングしました。
その遺伝子DNAの塩基配列を決定することにより、この遺伝子群の発現制御機構
(異化代謝産物抑制)を推測することができました(図参照)。そこで、この調節に関わる
大事な遺伝子に変異を与えようと考えています。つまり、この異化代謝産物抑制という遺伝子発現制御機構を
壊すことにより、この菌の糖に対する好き嫌いをなくしてやることができるはずです。
すると、キシロース等のペントースもブドウ糖などのヘキソースと同様によく利用するようになり、
しょう油中のペントースを少なくして、黒くなるのを防ぐことができると踏んでいます。
 これまでの成果
これまでの成果
- 糖一般の細胞への取り込み系であるPTSシステム(phosphoenolpyruvate dependent
sugar phosphotransferase system)の構成メンバーであるHPrタンパク質の精製
Arai et al., Biochem. Int. 27, 275-279 (1992)
- キシロース利用系遺伝子群のクローニングとそのDNA塩基配列の決定および
キシロース利用系遺伝子群発現制御機構の推測
Takeda et al., Appl. Environ. Microbiol. 64, 2513-2519 (1998)
 今後の発展
今後の発展
- キシロース利用系遺伝子群発現制御の分子機構と調節遺伝子への変異導入
- 最終的に、そのような変異導入菌を用いた、おいしくかつ黒くならないしょう油の生産
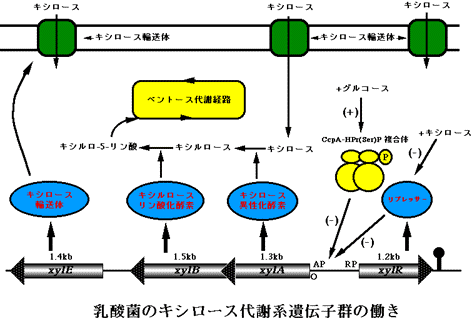 私達はまずこの菌(Pediococcus halophilus)のキシロース利用系酵素の遺伝子群をクローニングしました。
その遺伝子DNAの塩基配列を決定することにより、この遺伝子群の発現制御機構
(異化代謝産物抑制)を推測することができました(図参照)。そこで、この調節に関わる
大事な遺伝子に変異を与えようと考えています。つまり、この異化代謝産物抑制という遺伝子発現制御機構を
壊すことにより、この菌の糖に対する好き嫌いをなくしてやることができるはずです。
すると、キシロース等のペントースもブドウ糖などのヘキソースと同様によく利用するようになり、
しょう油中のペントースを少なくして、黒くなるのを防ぐことができると踏んでいます。
私達はまずこの菌(Pediococcus halophilus)のキシロース利用系酵素の遺伝子群をクローニングしました。
その遺伝子DNAの塩基配列を決定することにより、この遺伝子群の発現制御機構
(異化代謝産物抑制)を推測することができました(図参照)。そこで、この調節に関わる
大事な遺伝子に変異を与えようと考えています。つまり、この異化代謝産物抑制という遺伝子発現制御機構を
壊すことにより、この菌の糖に対する好き嫌いをなくしてやることができるはずです。
すると、キシロース等のペントースもブドウ糖などのヘキソースと同様によく利用するようになり、
しょう油中のペントースを少なくして、黒くなるのを防ぐことができると踏んでいます。 これまでの成果
これまでの成果 今後の発展
今後の発展 "研究紹介"のホームページに戻る
"研究紹介"のホームページに戻る 山登研ホームページ
山登研ホームページ