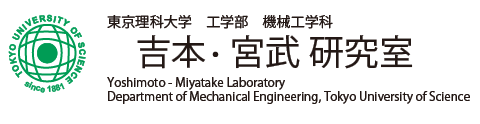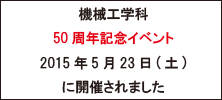3D設計研究会 過去の研究会
第6回 研究会 2025年10月15日(水)
講演題目および概要
「魔改造の夜」から考えるものづくりの未来
崎坂 亮太 氏(株式会社IHI 技術開発本部 統合開発センター 開発企画部)
[概要]
「魔改造の夜」はおもちゃや家電を6週間でモンスターに改造し、ライバルチームとの協議に挑む、エンジニアのアイデアとテクニックを競う技術開発エンタメ番組である。
講演者らはこの番組に挑戦し、誰もやったことがないことに挑戦する困難に直面した。即ち、普段の仕事は先人が作った道の延長線を行っているだけで、ゼロから道を作った経験がないことを突き付けられた。
この困難に抗った事例と、そこから得た気づきを会社の仕事(=ものづくり)にどのようにフィードバックしていくかについて、講演者の考えを紹介する。
第5回 研究会 2025年6月11日(水)
講演題目および概要
「魔改造の夜 第3夜への挑戦から考える設計の本質」
井上 雄介 氏(SOLIZE株式会社 上席執行役員)
[概要]
魔改造の夜は超一流のエンジニアたちが極限のアイデアとテクニックを競う技術開発エンタメ番組で、「子どものおもちゃ」や「日常使用の家電」をわずか6週間で改造して競争する。
講演者は元Hondaのオートバイレーサー開発責任者で、2020年9月にSOLIZEへ転職。2021年8月放送の 魔改造の夜 第3夜に「Sライズとして出場し扇風機と赤ちゃん人形の改造を行った際にプロジェクトマネージャーをつとめた。今までに誰もやったことがない改造を、ドキュメンタリー形式で伝える番組の中には、設計の本質が詰まっている。 実際の取り組みと改造事例をもとに、設計が本来持つ役割を考える。
第4回 研究会 2024年12月12日(木)
講演題目および概要
・話題提供1 14:35~15:15松本 陽司 氏(サイバネットシステム株式会社)
タイトル:バーチャルリアリティをベースとした解析評価とAIの活用
概要:CADや解析結果のCGを実際に実物が存在するかのように表示するバーチャルリアリティ技術(VR)は、HMDの普及により設計・製造分野への普及が加速しています。VRを使用することで、「顔を近づける」「パーツを掴んで動かす」といった自然な操作でCADや解析結果を確認でき、データや空間をネットワークで共有することにより、専門分野の垣根を超えた議論が可能になります。またそれらにAIを組み合わせることで、動かしたパーツが空力に与える影響をその場で確認したり、議論の結果を「要約・比較」を行えるようになり、アイデアの「生成・共有・集約」が加速されます。本発表では、このようなVR技術の現状と、AIを利用した将来の展望についてご紹介します。

Quest3組付けデモ体験の概要
・コーヒーブレイク
・話題提供2 15:40~16:20
井形 哲三 氏(EPLAN JAPAN)
タイトル:デジタルツイン〜電気設計も3D化
概要:製造機械、生産設備において新規製品を開発する際には、メカサイドでの仕様決定から始まるが、その全体のシステムをコントロールする要の装置である。また、メカサイドの設計変更に伴うシステムの再調整から、それを稼働させるための制御盤の仕様変更(制御盤の位置、大きさなどの変更)は大きな労力を必要とする。現状では、いまだに3Dでのメカエレ連携できていなく、しわ寄せを吸収しているのが、電気設計、制御部門とも言える。メカエレ3D化と製造プロセスを連動する事で、制御と機械の連動が可視化も可能となり、無駄な変更、手戻りも防ぐことができ製品およびシステムの完成度と納期が短縮される。本発表では、電気設計から制御盤製造の3D化を紹介する事で、今後の3D電気設計の現状と将来像を紹介します。
第3回 研究会 2024年9月12日(木)
講演題目および概要
(1). 格子運動論スキームによる熱流体問題のトポロジー最適化
田邉 雄太 氏(東京理科大学大学院工学研究科機械工学専攻)
[概要]
トポロジー最適化はその自由度の高さから近年注目を集めている設計手法であるが、設計変数の更新量を求める際に必要な感度の計算時間およびメモリ消費が大きいという問題がある。このコストを抑えるのに格子ボルツマン法(LBM)を用いた手法が提案されてきたが、計算速度の向上は達成されたものの、特に非定常・熱流体問題でメモリ消費が大きいという課題が残されていた。本研究ではLBMから派生し、メモリ消費を抑えた解法である格子運動論スキーム(LKS)を用いたトポロジー最適化手法を提案し、非熱流体/熱流体に関する定常/非定常問題の数値計算例を示した。
(2). nTopによるAM向け設計プロセスのご紹介~軽量化~
安居 涼香 氏(株式会社テクノソリューションズ 東京本社)
[概要]
トポロジー最適化やラティス設計も可能なnTopというソフトウェアを、軽量化プロセスを例に用いてご紹介します。
第2回 研究会 2024年6月6日(木)
講演題目および概要
(1). 設計図面変革:3Dデジタル・バーチャルモデル
内田 孝尚 氏((国研)理化学研究所 研究嘱託)
[概要]
3D/Digital/Virtualを用いた設計/開発/ものづくり環境となり、設計段階で設計仕様、製造要件、製造品質の検討、決定が可能となった。
そのコアとなる図面形態について説明致します。
(2). CADデータを利用したCAMシステムの活用方法
白原 直樹 氏(ジェービーエムエンジニアリング株式会社 大阪支店営業部)
[概要]
CAD/CAMを使った切削加工の事例をご紹介します。
第1回 研究会 2024年3月7日(木)
講演題目および概要
(1). 「東京理科大学工学部機械工学科におけるCAD・CAEの活用について」
東京理科大学 宮武 正明 氏
[概要]
機械工学科および宮武研究室におけるCAD・CAEツールの使用事例・概要をご紹介します。
(2). 「粉末冶金プロセスCAEのご紹介」
サイバネットシステム株式会社 石田 智裕 氏
[概要]
貯蔵・搬送、混合、充填、成形、焼結、後処理といった粉末冶金のプロセスで用いられるCAEをご紹介します。紹介します。
日本設計工学会 CAD/CAE研究会 過去の研究会
CAD/CAE 研究会は1998 年に発足し、2004 年度より設計工学会内に設置された研究会として活動してまいりました。毎回、企業および大学から講師を招き、CAD/CAE の企業内あるいは大学における活用方法、教育方法などについて議論を行っております。ご講演内容は、CAD/CAE に携わる方々にとって非常に有益で示唆に富むものとなっております。
第71回 研究会 2017年3月6日(月)
講演題目および概要
(1). 「CAD/CAEを活用した等身大脚型ロボット開発の事例紹介」
早稲田大学高等研究所 助教 橋本 健二 様
[概要]
講演者は3次元CAD設計ソフトウェアSOLIDWORKSを使用して約15年にわたり等身大
の脚型ロボットを開発してきた.本講演では,これまでに講演者が開発に携わった
2足ヒューマノイドロボットWABIAN-2や人間搭乗型2足歩行ロボットWL-16,
災害対応を目的とした4肢ロボットWAREC-1等の具体例を通して,CAD/CAEの
活用事例を紹介する.
(2). 「熱溶解積層方式3Dプリンタについて」
武藤工業株式会社 設計計測事業部 金子 俊一 様
[概要]
2014年から発売を開始したデスクトップ3Dプリンタ「3DMagiX」は、
国内No1の販売実績を誇ります。「3DMagiX」の造形方式である
熱溶解積層方式の特徴や、造形テクニック、ユーザ事例を中心に
紹介します。
第70回 研究会 2016年11月4日(金)
講演題目および概要
(1). 「実際の設計製造現場における3Dモデルを活用した最適化応用例について」
熊本県商工政策課 課長補佐 土村 将範 様
[概要]
近年のコンピュータ技術の飛躍的な進歩、さらには3Dプリンタ等の最新製造装置の
低価格化と普及に伴い、中小企業等のものづくり現場において、設計製造だけでなく
開発や検証などの工程でも、3Dモデルデータの利活用が広く普及しつつある。
本発表では、地域企業などの製造現場や試作行程、さらには研究開発等において、
CAD/CAM/CAE等で3Dモデルを利用することで、形状最適化や性能向上、またコストダウン
など、実際の製品改良や最適化を達成した応用事例を紹介する。
(2). 「転がり案内における接触部の静剛性・減衰特性とCAD/CAEを用いたそのモデリング手法」
東京工業大学 科学技術創成研究院 未来産業技術研究所 研究員 酒井康徳 様
[概要]
近年,工作機械の低コスト化や高性能化が求められており,CAD/CAEを用いた機械設計と
制御設計を同時に行えるモデルベース開発への期待が高まっている.
この技術を実現するためには,工作機械の動剛性を定量的に予測可能な技術の確立が不可欠である.
工作機械の動剛性は案内や軸受の静剛性・減衰特性の影響を大きく受けるため,
これらの特性を明らかにし,そのモデリング手法を構築することが求められる.
そこで,本講演では,工作機械で広く使用される転がり案内の静剛性・減衰特性に関する
知見に触れるとともに,CAD/CAEによるそのモデリング手法について述べる.
第69回 研究会 2016年6月3日(金)
講演題目および概要
(1). 「粒子法CFDソフトウェアParticleworksの製品開発への応用における現状と課題」
プロメテックソフトウェア株式会社 戸倉 直 様
[概要]
流体工学の分野では、従来よりメッシュベースのCFDソフトウェアがCAEの世界で用いられ、豊富な実績が構築されている。しかし複雑な形状の解析空間に計算用メッシュを生成することは未だに多くの工数を要する複雑な作業となっている。これに対し、粒子法の一種であるMPS(Moving
Particle Simulation)法をベースとした商用CFDソフトウェアが開発さ
れ、多くの産業分野で設計開発等の実務に用いられるようになってきた。粒子法CFDソフトウェアはその特徴を活かして、メッシュベースのアプローチではモデル化が困難な問題に対して適用されている。Particleworksはそのようなソフトウェアのひとつであり、本講演では他の数値計算手法との比較により、MPS法の特徴を示すとともに、CAEツールとしてのParticleworksの機能の概要および企業における最近の応用事例について紹介する。また、粒子法ソフトウェアに対する実務面からの要求と今後の課題について概観する。
(2). 「人と機械の融合を目指したマンマシンインターフェースの開発」
株式会社メルティンMMI 粕谷昌宏 様
[概要]
従来、生体信号といえば高額で大掛かりな装置による計測が必要であったが、近年の電子機器の小型化・高性能化および低価格化に伴い、ポータブル機器での生体信号の利用が一般に広がりつつある。本講演では、生体信号を用いたマンマシンインターフェースの開発とその応用について述べる。特に、現在メルティンMMIにおいて開発を進めている、筋電信号を用いた電動義手と汎用筋電インタフェースの特徴およびその目指す世界を紹介する。メルティンMMIは、世界から身体的なバリアを取り除くことをスローガンに活動する、電気通信大学発のベンチャー企業である。義手は身体を代替するものであるのに対し、メルティンMMIでは身体を拡張するアプローチについても開発を進めていることを述べ、この領域の世界の動向についても紹介する。
第68回 研究会 2016年2月29日(月)
講演題目および概要
(1). 「乱流及び乱流燃焼のCFD:直接数値計算とモデリング」
東京理科大学 工学部第一部 機械工学科 福島 直哉 様
[概要]
コンピュータのハードウエア及びソフトウェアの発達にともない,様々な産業分野における熱流体機器の設計において,CFDが活用 されている。一 方,CFDで用いられるモデルの予測精度は十分とは言えず,高精度なモデルの開発が求められている。そこで,乱流及び乱流燃焼における直接数値計 算(DNS)の現状とDNS結果を用いた新たな高精度モデルの開発について紹介する。
(2). 「Virtual Test Drivingがもたらす自動車開発における新しい視点
~ 出来る事から始めよう,自動車開発におけるシミュレーション技術の活用手法~」
IPG Automotive株式会社 小林 祐範 様
[概要]
自動車開発においてもモデルベース開発(MBD)が盛んに議論されており,様々な分野に適用した事例が増えてきている.ハイブリッド,電気自動車を中心とした自動車の電動化,自動運転を目指す各種ADAS機能の開発など,年々自動車の開発は複雑化を増し,如何に開発の早い段階で「車両レベル」のシミュレーションを実施するかが課題となっている.このような車両レベルのシミュレーションを実施するには,様々なシミュレーションツールを連成する事が出来るかが鍵となり,シミュレーションプラットフォームの構築も徐々に重要になってきた.IPG Automotiveが使命としている「Virtual Test Driving」はもう一歩この考えを先に進め,車両を取り巻く環境,交通流,自動車を操作するドライバ等を含めたすべての環境をバーチャルに実現する事を目指している.どのようにVirtual Test Drivingを実現しているのか,欧州の事例を紹介しつつ,日本の自動車業界にどのように貢献する事が出来るのかを考察する.
第67回 研究会 2015年11月9日(月)
講演題目および概要
(1). 「電気通信大学における機械製図の教育法について」
電気通信大学 大学院 情報理工学研究科 知能機械工学専攻 橋本卓弥 様
[概要]
電気通信大学の知能機械工学科では,現在,2年生の専門科目として「メカノ
デザイン」という科目を開講しており,機械製図の基礎について教育を行ってい
る.また,3年生では「マシンデザイン」という科目を開講しており,歯車減速
機の設計・製図および3D-CADの使用方法について教育を行っている.本講演で
は,まず,本学ならびに本学科の概要を紹介し,次に,私が主に担当している
「メカノデザイン」の教育内容を中心に,電気通信大学における機械製図の教育
方法について紹介する.
(2). 「バーチャルエンジニアリングとバーチャルテストについて」
株式会社 本田技術研究所四輪R&Dセンター
デジタル開発推進室 CISBL シニアエキスパート内田 孝尚様
[概要]
距離/時間/要素を同一の場」で検討できるVE(Virtual Engineering) /VR(Virtual Reality)が注目を集め、加速展開がはじまっている。
「3D /Digital/IT駆使の設計・ものづくり」時代になり,高い創造性を生かした設計を行うことの出来る環境となった今日、
CAE駆使の創造設計(Creative Design with CAE)とそれらを効果的に活用するVEの動向を説明する.の習得に必要な教育について
議論したいと考えています。
第66回 研究会 2015年8月3日(月)
講演題目および概要
(1). 「PTC Creo用のEラーニング教材(PTC University)について」
PTCジャパン株式会社 佐伯 菜々 様
[概要]
(2). 「~「カン」を磨き応用力を育む~
CAE活用のための技術教育についての議論」
メカニカルCAE事業部 技術部 石田智裕 様
[概要]
汎用のCAEツールが最初にリリースされてから50年近くが経過し、
多くの企業が「ものづくり」のプロセスにCAEを組み込むようになりました。
しかしながら、CAEを導入した多くの現場で、以下のような声を聞きます。
「決まった操作は出来るけれど、結果をどう読んだら良いのか分からない。」
「想定外のことにどう対処して良いか分からない。」
「大学で材料力学を学んだはずだが、実務で使えない。」
本講演では、このような状況を踏まえ、サイバネットが提供する
技術教育サービス「CAEユニバーシティ」を例に挙げながら、
CAEを使う人に必要な技術や技能、およびその習得に必要な教育について
議論したいと考えています。
第65回 研究会 2015年4月27日(月)
講演題目および概要
(1). 「ドライビングシミュレータを用いた横滑り防止装置の効果評価」
東京理科大学 工学部 機械工学科 講師 林 隆三 様
[概要]
自動車の事故防止技術として4輪のブレーキ制御を用いた横滑り防止装置(ESC)が
実用化されていますが,その効果の向上のためには,横滑り防止装置の作動状態と
ドライバの操作の関係を明らかにすることが課題となっています.
本講演では,その基礎検討として,ドライビングシミュレータを用いて
ESC作動中の実際のドライバの操舵特性について分析した事例について紹介します.
(2). 「東京大学機械系学科及び社会人実務者向けのCAE 教育の紹介」
東京大学 大学院 工学系研究科機械工学専攻 教授 泉 聡志 様
[概要]
CAEはコンピュータとソフトウェアの急速な発展を背景に,
機械設計分野に広く深く浸透しつつある.
しかしながら,CAEを使いこなすための技術者のスキルは十分とは言えず,
様々な問題が発生している.また,使いこなすための教育体系も確立されていない.
本講演では,東京大学工学部機械工学科で長く行われてきた有限要素法を
中心としたCAEに関する講義・演習の試みについて紹介するとともに,
筆者らが行ってきた社会人教育の一例として,
日本機械学会材料力学部門マルチフィジックスの実験/計算技術の高度化に関する
研究会における活動の紹介を行う.
第64回 研究会 2015年1月26日(月)
講演題目および概要
(1). 「工作機械熱変位補償技術の研究」
株式会社ジェイテクト 研究開発本部 若園 賀生 様
[概要]
マシニングセンタをはじめとする工作機械は、設置環境の室温変化により機械構造体が熱変形する。そのため、工具とワークの相対位置が変化して加工精度が悪化する原因となる。そこで、工具とワークの相対変位を補償する技術が求めら れている。工具とワークの相対変位分だけ軸移動量を補正すればよいが、工具とワークの相対変位を直接測定するのは現実的でないため、コラムやベッドなどの機械構造体の各部の温度から熱変位を推定し、補償する。これを実現するため 、有限要素法(FEM)をベースとしたCNCに搭載可能な熱変位推定手法を開発した。この手法によれば、非加工時間を延ばすことなく、作業者の技量に依存せず、また、比較的安価なイニシャルコスト、ランニングコストで工作機械の熱変位補 償が可能となる。
(2).「配管の水撃作用と固液連成解析」
東京工業大学大学院理工学研究科 機械物理工学専攻 准教授 因幡 和晃 様
[概要]
配管内を伝播する水撃作用は管壁中のたわみ波と水中の圧力波が相互に連成しながら伝播することが知られている。本講演では、水撃作用の固液連成解析事例の紹介や新しい被害低減方法を紹介する。
第63回 研究会 2014年10月27日(月)
講演題目および概要
(1). 「ANSYS と音響解析ソフトWAONを用いた流体音解析」
サイバネットシステム株式会社 森 正明 様
[概要]
自動車や家電製品の静音性、またオーディオ機器等でのさらなる音質の追求など、音響解析のニーズが高まっています。音の音源は代表的なものとして構造物の振動によるものと、流体運動によるものがあります。弊社では、最近、自社開発の境界要素ソルバーである、音響解析ソフトウェア「WAON」に流体音解析機能を実装しました。本講演ではWAONとFEMを使用した振動音響解析の事例やWAONとCFDを使用した流体音解析事例、および流体運動によって発生した音が構造物を透過する現象について計算手順を交えて紹介します。
(2). 「マシニングセンタ主軸システムを課題とした3D-CADの設計教育事例について」
東京理科大学 工学部第一部 機械工学科 助教 中村 恭子 様
[概要]
講演者の出身である上智大学機能創造理工学科では,学部3年次における機械設計の実践的な講義科目として,歯車変速機構を活用したマシニングセンタ主軸システムの設計を行っている.本講演では,3D-CADおよびCAEを使用した主軸モデリング設計法と教育法について,大学の許可を得た範囲を紹介する.
第62回 研究会 2014年7月18日(金)
講演題目および概要
(1). 「Additive Manufacturing技術を応用した金属製3次元セル構造の作成方法について」
東京理科大学 工学部第一部 機械工学科 准教授 牛島 邦晴 様
[概要]
近年,航空機の基本構造部材として,ハニカムに代わる軽量かつ高強度な構造の
開発が求められています.本講演ではAdditive Manufacturing技術を応用し,
金属にレーザー光を照射して作成できる微細な3次元オープンセル構造
(=マイクロラティス構造)について,その作成技術と応用例について紹介します.
(2).「GStudio MAXによるCTデータを利用したマテリアル情報と形状の解析」
ボリュームグラフィックス株式会社 佐藤 充男 様
[概要]
近年、産業用CTはR&Dのみならず、モノづくりにおける多くの局面においての利用が進んでいる。
本講演では、透過画像をベースとするCTデータの「内/外部情報をあわせ持つ」という特徴を活かした、
VGStudio MAXによる様々な解析とその適用例を紹介するとともに、
産業用CTに関する動向についてもあわせて紹介する。
第61回 研究会 2014年4月21日(月)
講演題目および概要
(1). 「粒子法を用いたCFDの産業応用例の紹介」
東京理科大学 工学部第一部 機械工学科 高橋 亮平 様、山本 誠 様
[概要]
現在、コンピュータの性能向上により、多くの産業分野においてCFDが活用されている。
その中でも近年注目を集める流体解析手法である粒子法の特徴および産業分野への適用例について紹介する。
(2).「歯科用CAD/CAM「セレックACオムニカム」について」
シロナデンタルシステムズ株式会社 ティンシュマン様、西澤 省三 様
[概要]
世界初となる歯科用CAD/CAMは今から約30年前からスタートしました。
その後、コンピュータの進化に伴いより操作性の良いソフトウェアの開発とハードウェアの改良がなされ、
世界中の多くのドクターにご使用いただいております。
第60回 研究会 2014年1月27日(月)
講演題目および概要
(1). 「先進的なダイレクトモデラーSpaceClaimの適用による、様々なワークフローでの効果について」
スペースクレイム・ジャパン株式会社 代表取締役社長 小林 明 様
[概要]
SpaceClaimダイレクトモデリングテクノロジーの活用が、構想設計から生産に至る様々な場面で急速に浸透してきている。
本講演では、フィーチャーベースCADとは大きく異なる先進的な技術、
既存CAD/CAE/CAMとの共存による効果などについて、
最新バージョンSpaceClaim 2014の新機能(クラウド活用も含む)も交えながら紹介する。
(2).「3次元直接描画のインターフェースの評価」
東京工科大学 コンピュータサイエンス学部 メカトロニクスコース 助教 三橋 郁 様
[概要]
3次元モデルを設計するツールは3D-CADがほとんどである.3Dモデリングを直感的に操作できる方法として,
3D Direct Drawing手法が提案されてきたが,画期的に普及には至っておらず,
評価する手法すら確立されていない.
そこで本研究では,設計者の意匠通りの3次元直接描画手法を提案することを目的に,
自由曲面/ポリゴン平面,立体描画の描画手法を提案し,品質工学を用いて描画方法の評価を行った.
一方で,ARToolKitでの3次元直接描画手法は研究者側からユーザーインターフェースを
強制的に指定しているため,操作者は直感的な描画を行っているとは限らない.
そこで,本研究ではMicrosoft Kinectを用いて,操作者に面や立体形状のジェスチャーを行わせ,
その動作に基づいた形状を表すシステムを構築した.これにより,3次元直接描画手法の
インターフェース評価を決定し,容易な3次元直接描画手法の提案が生まれることが期待できる.
第59回 研究会 2013年10月28日(月)
講演題目および概要
(1). 「設計から製造での開発領域でのVR技術を使った試作レスへのチャレンジ」
ESI Group Asia 副社長 井形 哲三 様
[概要]
長年にわたる製品設計現場とラピッドプロトタイプ業界の知見から見た視点で、
本来の試作レスを行うためのプロセス及び必要要素技術をCAEソフトウエアベンダー
としてESI社が持つシミュレーション技術を通じて、製造領域から生産準備期間の短縮、
試作コストの削減の両立をVR技術の進化を通して、バーチャルな環境の中で実現する事を提案する。
当講習会では、ESIが考えるVRの位置づけを海外の事例を含め、説明する。
(2).「東京理科大学 工学部第一部 機械工学科におけるCAD/CAEを用いた教育の概要」
東京理科大学 工学部第一部 機械工学科 講師 宮武 正明様
[概要]
東京理科大学工学部第一部機械工学科では、1990年台初頭に製図室に約60台の
CAD/CAEシステムを導入して以来、約20年にわたり、様々な授業において使用している.
本研究会では、それらCAD/CAEの活用事例について紹介する。
第58回 研究会 2013年7月22日(月)
講演題目および概要
(1). 「速度依存性摩擦モデルの提案と有限要素解析への適用:スティックスリップ運動を中心に」
横浜国立大学大学院工学研究院 システムの創生部門 准教授 尾崎 伸吾様
[概要]
本講演では、先ず、講演者らが提案した速度依存性摩擦モデルについて紹介する。本モデ
ルは状態変数とその発展則が導入されているため、基本的なすべり摩擦の速度依存性を記
述可能である。次に、提案摩擦モデルを有限要素法に実装するとともに,比較的低速すべ
り領域で問題となるスティックスリップ運動の解析例について紹介する。
(2).「設計者自らが手軽に利用できる本格的CAEソフト「Femtet(R)」のご紹介」
ムラタソフトウェア株式会社 販売推進課 辻 剛士 様
[概要]
Femtetは「設計者自らが電卓のように気軽に利用するCAEソフト」というコンセプトで
電子部品メーカー「村田製作所」で開発され、30年以上設計の現場で活用されてきた
日本発の有限要素法解析ソフトである。本講演ではFemtetの成り立ちや販売にいたる経緯、
解析機能・活用事例についてデモを交えて紹介する。
第57回 研究会 2013年4月22日(月)
講演題目および概要
(1). 「非線形構造解析ソフトADINAを使った大学院講義事例の紹介」
横浜国立大学環境情報学府・環境情報研究院 講師 松井和己様
[概要]
大学院環境情報学府では,CAEソフトウェアADINAを用いて「数値シミュレーションの
妥当性をどうやって検証するか?」を主題とした講義を行っている.有限要素法がどのよ
うな特性を持っているのかを理解して,正しく利用できることを目的として行っている講
義の一部を紹介する.
(2).「数値サーマルマネキンを用いた暖房室内環境評価手法の開発」
東京理科大学工学部建築学科 環境工学研究室 教授 倉渕 隆 様
[概要]
数値サーマルマネキンを用いた人体表面の対流熱伝達率の予測精度の検証を実験との比較
に基づき行った上で、居室及び浴室に設置された暖房システムの効率評価に応用した事例
について紹介する。
第56回 研究会 2013年1月28日(月)
講演題目および概要
(1). 「医学領域におけるCFD解析~脳動脈瘤~」
慈恵医科大学 脳外科 高尾 洋之様
[概要]
近年,医学領域においてCFDにおける血流解析が頻繁に行われている.
流体力学の専門的知識を応用すれば様々な病気の治療につながっていく可能性がある.
我々は,その中でも現在行われている脳動脈瘤血流解析における意味と
今後について解説する.
(2).「日本発条㈱の研究開発におけるCAEの活用事例の紹介」
日本発条株式会社 研究開発本部 開発部 冨永 潤 様
[概要]
日本発条㈱の自動車、情報・通信、産業・生活などの分野の新製品開発において、メカニ
ズムの解明から新製品の提案について、CAEを活用した事例を紹介する.
第55回 研究会 2012年11月5日(月)
講演題目および概要
(1). 「3Dデータを用いた製品設計部門と製造部門のコンカレントエンジニアリング の実現」
オリンパス株式会社 ものづくり革新センター 開発ソリューション本部 DEM技術部 土井 大介様
[概要]
製品開発部門と3Dデータで連携する事で、製造部門での工数削減と期間短縮を実現した生産技術
の取り組みを紹介する。 また、国内外の製造拠点間のデータ管理の仕組みについても紹介する。
(2).「数式処理を用いたマルチボディダイナミクスのシミュレーションと制御」
サイバネットシステム株式会社 CTOプロジェクトセンター センター長 CTO 石塚 真一 様
[概要]
近年,数式処理を用いたマルチボディダイナミクスのシミュレーションが注目されている.
本講演では,同システムをレビューし,数式処理の利点と,それを応用した制御設計手法を紹介する.
第54回 研究会 2012年7月23日(月)
講演題目および概要
(1). 「機構解析ソフトを用いた偏心式ローラ減速機計算」
NTN株式会社 自動車事業本部 CAE技術部 今田大介様
[概要]
偏心式ローラ減速機の動的機構解析について報告する。偏心式ローラ減速機の基本構造、
解析モデル、実験との整合性、および工数削減のため設計者自身が使用できる自動解析シ
ステムについて紹介する。
(2).「インタラクティブに統合されたCADとCAEについて」
東京大学大学院 情報理工学系研究科 コンピュータ科学専攻 梅谷信行様
[概要]
一般的にCAEはCAEと別々のシステムとして扱われているために,CAEは主に与えられ
た性能要求を満たすかどうかの確認にのみ使われ,創造的なデザインの過程を支援するた
めにはあまり使われていません.本発表では,リアルタイムのシミュレーションをインタ
ラクティブな形状モデリングに統合させることにより,創造的なデザインを支援する私の
研究について紹介します.
第53回 研究会 2012年4月16日(月)
講演題目および概要
(1). 「半導体露光装置の大規模構造解析」
㈱ニコン 精機カンパニー 開発本部 主任研究員 神山隆英様
[概要]
半導体露光装置は、史上最も精密な機械と呼ばれている。開発段階では、微細化要求と開
発期間短縮の為、CAEを積極的に活用してきた。本講演では、ナノメータ オーダの精度
が求められる、露光装置の構造解析のポイントを整理し、それらを実現する為の大規模
FEM作成ノウハウや実験コリレーション、また、過渡応答解析や制御系解析への利用など
を、実例と共にご紹介する。
(2).「企業技術者・学部生・大学院生・高専学生を対象とした夏休み設計セミナー」
京都大学大学院工学研究科マイクロエンジニアリング専攻教授 松原厚様
[概要]
このセミナーは,設計の楽しさと設計の本質を理解してもらうことを目的として,2001年
から毎年夏休みにボランティアで開催してきた.セミナーでは,8~9名からなる企業のエ
ンジニアと学生からなる協同チームで2日半にわたって,設定された設計課題に取り組み,
「現在何が重要で,何を検討しなければならないのか」「設計の根拠は何か」を考えなが
ら論理的に設計を進める.3次元CADとCAEは,あくまで設計仕様の検証のための道具
として用い,大半は模造紙を書きながらのデスカッションが続く.受講者も講師も2日半
の中で様々な問題に遭遇し,10年たった今でも試行錯誤の連続となっている.本講演では
この経験から得た機械設計と教育の難しさについて話をする.
第52回 研究会 2012年1月23日(月)
講演題目および概要
(1). 「設計力強化のためのCAE活用と3Dデータ標準化」
㈱本田技術研究所 四輪R&Dセンター 開発推進室 CISBL 内田孝尚様
[概要]
設計者が3D設計を行なうことが当たり前になり、設計者がCAE活用した仕様検討&熟成
も普及して来た。その普及状況と今後の方向性を述べるとともに3D設計環境における課
題と3Dデータの標準化について述べる.
(2).「き裂進展解析システムの開発と解析事例」
東京理科大学理工学部機械工学科 教授 岡田 裕様
[概要]
発表者らが開発してきた、き裂進展解析システムについて報告する。このき裂進展解析シ
ステムは、テトラ(四面体)有限要素を使用し、自動解析モデル生成ソフトウエア、仮想
き裂閉口積分法(テトラ要素用VCCM, Virtual Crack Closure-Integral Method)、並列有限要
素法解析プログラム(ADVENTURE Solid)を繋ぎ、解析の自動化をしたものである。講演
では、各要素技術に関する簡単な説明と、解析例の紹介をする。
第51回 研究会 2011年11月7日(月)
講演題目および概要
(1). 「設計手法としての価値工学の適用」
産業能率大学総合研究所 経営管理研究所 主任研究員 橋本公一様
[概要]
製造業における製品設計の場では、CAD/CAEとともに実践的な設計技術の一つである価値工学
(Value Engineering)が適用され、製品の機能・原価・納期に関して期待される成果を創出している。
本講演では、こうした価値工学における設計問題解決の基本的考え方とプロセス、その中心技術である
機能分析法、機能評価法、設計解への創発法について解説する。
(2).「次世代ものづくり環境-エンジニアリングクラウドへの取り組み」
富士通アドバンストテクノロジ㈱ エンジニアリングクラウドプロジェクト長 安田 満様
[概要]
クラウドコンピューティング時代に向け、製造業における「ものづくり環境の変化」に対応した、業界初の取り組みとなる
「エンジニアリングクラウド」についてご紹介する。「エンジニアリングクラウド」は「富士通のものづくり/プロダクト
/サービスのノウハウ・技術を結集したものであり、富士通グループ社内での取り組みを、顧客のニーズにあわせた
SaaSサービス・PaaSサービスを提供する予定である。エンジニアリングクラウドを実現するうえで重要な
高速画像圧縮技術や今後の展開などについてご紹介する。
第50回 研究会 2011年7月11日(月)
講演題目および概要
(1). 「地球温暖化を防ぐ設計工学 - マルチドメインシミュレーションシステム開発」
いすゞ自動車シニアスタッフ 東京理科大学工学部機械工学科講師(非常勤) 高田 博様
[概要]
設計工学としては、今後、地球環境を設計するような大きな枠組みが必要になってくることが考えられ,
それを実現するためのシステム開発が必要となっている。現時点では、環境も含めた自動車の企画用検討
システムが開発されており、この検討システムについて解説する.さらにこのシステムは,
自動車だけではなく広く一般的な機械にも適用可能であり,グリーンイノベーションへ向けて
課題解決ツールとしての可能性について述べる。
(2).「X-FEMに基づく流体構造連成解析手法とそのCAD/CAE展開」
独)産業技術総合研究所 先進製造プロセス研究部門 研究員 澤田有弘様
[概要]
本講演ではCAE(Computer-Aided Engineering)やSBD(Simulation-Based Design)に
適した計算手法を会場の皆様と議論することを一つの目的に,その題材としてX-FEMを活用した
CAD/CAE統合型解析フレームワークの研究開発を紹介する.また,基盤技術となっている非線形流体構造連成解析手法と
その適用事例を幾つか紹介する.