

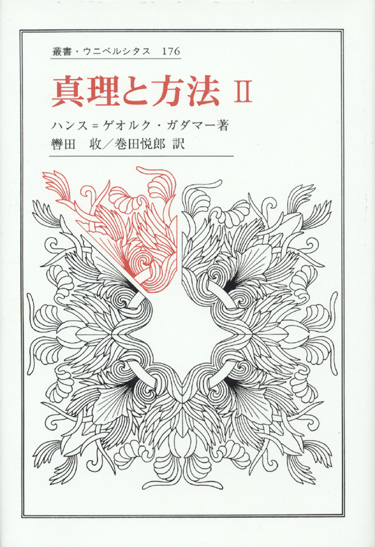 |
「理解はそれ自身、主観性の行為としてよりは、過去と現在がたえず互いに他に橋渡しされている伝承の出来事への参入として考えるべきである。」 ハンス=ゲオルク・ガダマーの『真理と方法』は、シュライアーマッハーやディルタイのロマン主義的な解釈学に対して、ハイデガーやヘーゲルに基づく存在論的な解釈学を打ち立てた記念碑的著作である。その核心部分とも言うべき第二部の邦訳。第一部の邦訳である第I巻の刊行(1986年)のあと長らく出版が待たれていた。 テクストを理解するとは、ガダマーによれば、著者と一体化することではなく、伝承されたテクストの意味に参与することである。ロマン主義と歴史主義に基づく伝統的な解釈学は、テクストをそれをテクストが成立した時代やそれを書いた著者の意図から理解しようとした。しかし、これは理解する者の歴史性を無視し、また、テクストが現代のわれわれに語りかけている内容の真理性を見失わせるものである。われわれは歴史家も含めて歴史的な存在であり、現在の観念や先入見を完全に中断できない。だが、優れたテクストは世代から世代へと現代まで伝承され、われわれにいつもすでに語りかけ、現在の観念や先入見を部分的に疑問に付している。理解はこのように自発的に起きている過去と現在の媒介を意識的に引き受けることである。 →第II巻(第二部)の要旨 |
|
目次 |
第II章 《解釈学的経験の理論》の要綱 第1節 理解の歴史性を解釈学の原理に高める a 解釈学的循環と先入見の問題 α ハイデガーによる理解の先行構造の発見 β 啓蒙思想による先入見の信用喪失 b 理解の条件としての先入見 α 権威と伝統の復権 β 古典性を例として c 時代の隔たりの解釈学的意義 d 作用史の原理 第2節 解釈学の基本問題を取り戻す a 適用という解釈学的問題 b アリストテレスの解釈学的アクチュアリティー c 模範としての法解釈学の意義 第3節 作用史的意識の分析 a 反省哲学の限界 b 経験の概念と解釈学的経験の本質 c 問いの解釈学的優位 α プラトンの対話術という模範 β 問いと答えの論理 原注 訳注 訳者あとがき |