■ 単結晶によるX線回折〜Laue Method〜
|
・結果
実験を行った結果、右のような写真が得られた。 この写真を解析して結晶の方位を出すのだが、今回はJavaAppletを用いて解析してみたい。 まず、任意の回転を与えた結晶格子から生じる回折線をシミュレートし、それに得られた写真を重ねる 事により、それらが一致する回転角をみつける。 また、各斑点についてどの面から反射されたものかを特定する「指数(hkl)」を定めるが、 その際に用いる逆格子ベクトルは立方晶系を代表して「単純立方格子」の基底を用いて定義した。 つまり、ここでは本来の体心立方格子の基底を使わず、結晶を「単純立方格子の単位格子の中心に 1つ余分な原子が入った構造」として捉えている。そしてそれに見合った構造因子によって 回折線の生成・消滅則が定義されている。 |
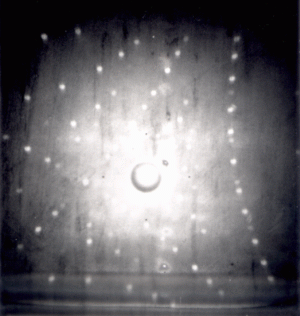
|
・シミュレーション(JavaApplet)
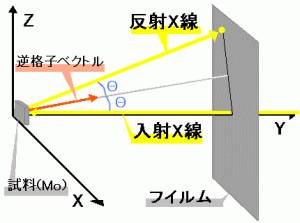 このアプレットは反射ラウエ法で得られる写真をシミュレートするもので、試料の角度を任意の値に設定したときの写真の斑点を描く事ができる。
実験で得られた写真も同時に表示する事ができるので、試行錯誤しながら実験写真とシミュレーションの斑点が重なるように各パラメータを調節すると、この写真を撮ったときに結晶がどちらの方向を向いていたかが分かる。
このアプレットは反射ラウエ法で得られる写真をシミュレートするもので、試料の角度を任意の値に設定したときの写真の斑点を描く事ができる。
実験で得られた写真も同時に表示する事ができるので、試行錯誤しながら実験写真とシミュレーションの斑点が重なるように各パラメータを調節すると、この写真を撮ったときに結晶がどちらの方向を向いていたかが分かる。各軸と試料、フィルムの関係は右図の通り。図からも分かるとおり逆格子ベクトルの延長とフィルム面の交点、入射X線とフィルムとの交点、斑点の位置はフィルム上一直線上にあり。図のような角度関係がある。ここでは基底ベクトルa1,a2,a3として(1,0,0)(0,1,0)(0,0,1) を用いて(正確な意味で基底ではない)、それらの点に回転を与え、得られたベクトルから逆格子ベクトルを計算し斑点を描画している。 |
|
<<結果>> 1.写真表示:ON 2.シミュレーション:ON 3.X軸回転:−2° 4.Y軸回転:37° 5.Z軸回転:14° 6.試料との距離:31mm 7.D-Space min:110×a/1000 (aは格子定数) 各パラメータを上記の値にすると、写真とシミュレーションによる斑点が一致する。 よって結晶はこれらの角度だけ回転している事が分かる。 逆格子ベクトルの大きさは、面間距離の逆数であることから、このアプレットでは「D−space min」で設定した値よりも面間距離が大きな面からの回折スポットのみ描画する。 入射X線の波長には有限の幅があるので、この結果から入射白色X線の波長領域が分かる。 ここではMoは体心立方格子であるということは既知として、それにあった構造因子、回折スポットの消滅則を用いた。 |