部門長挨拶
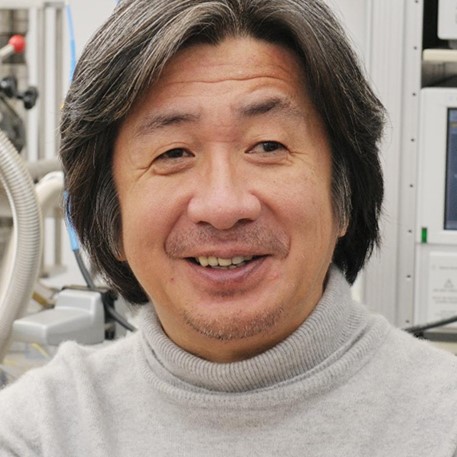
ナノ量子情報研究部門 部門長 蔡 兆申
背景
現在の量子コンピュータ研究が盛況を呈する契機となったのは、カナダのD-wave systems社が2011年に超伝導アニーリングマシンを販売開始したことでした。それは汎用量子コンピュータではなくて、最適化問題を解くのに適した、量子アニーリングマシンでした。
汎用タイプとしては、アニーリングに対して、ゲートタイプマシンと呼ばれる量子コンピュータがあります。先ごろGoogleがこのゲートタイプで、量子超越性を達成したという大きなニュースがありました。この結果は日本を含めた各国の政府、研究機関、研究者にゲートタイプの量子コンピュータの開発研究の重要性を改めて認識させる結果となりました。
我々が目指すもの
研究の中心である超伝導量子ビットには、従来の古典的半導体回路と同じように、エラー(誤り)が発生します。また外部雑音などによって、量子ビットの量子重ね合わせ状態(俗に言う猫状態)が壊れてしまう現象(デコヒーレンス現象)もあり、これもエラーの一要因となります。真の実用化という意味での量子コンピュータと呼ばれるシステムは、このような誤りに対する耐性を持ったシステムです。そこで本研究部門では、超伝導量子ビットを用いた様々な誤り耐性量子回路の開発を実施していきます。
世界では2050年までに誤り耐性型量子コンピュータの出現が期待されていますが、その実現に向けて本研究部門もその実現に貢献していきます. 集積性、操作性という観点から、超伝導素子が量子ビットとして最も適していると考えられています。しかし、超伝導量子ビットにも問題点があります。それはコヒーレンス時間がまだまだ短いという点です。量子ビットの研究の初期から、超伝導以外の物理システム、例えば光とかイオン、冷却原子、半導体といったものが研究されてきました。我々の研究部門でも、超伝導量子ビットだけでなく、スピンや光量子ビットの量子回路を追求していきます。
東大との共同研究
本研究部門のもう一つの研究活動として、東大との共同研究があります。
連携先は、東大のナノ量子情報エレクトロニクス研究機構と量子イノベーション協創センターです。研究テーマは、単一光子を用いた量子光学分野です。
部門長からのメーセージ
量子コンピュータ研究はここ数年、にわかに活況を呈しています。
ナノテクノロジーの進歩による量子ビットのコヒーレンス時間が長くなったことも理由の一つです。しかし実用化にはまだほど遠く、真の意味でエラー訂正機能を持った量子コンピュータの実現に向けた研究を加速する必要があります。

