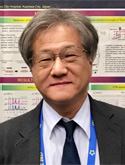本研究部門の構成メンバー・部門における役割
本研究部門では、以下の4つのグループが相互に連携することで、再生医療を加速する超細胞・DDS開発研究を推進します。
(1)超細胞・DDS開発グループ
超細胞の設計および開発と、細胞や各種生理活性物質の体内動態制御を目的としたDDSを開発します。細胞への新機能の付加、細胞スフェロイド・オルガノイドの構築、エクソソームに代表される細胞外小胞の利用などの視点から、これまでの細胞機能を超越する「超細胞」の開発を目指します。また、各種DDS技術を超細胞に適用し、疾患モデル動物等を用いた評価によりその有用性を検証します。
再生医療を加速する超細胞・DDS開発研究部門
電話(代):04-7124-1501(内)6451 メール:kusamori@rs.tus.ac.jp


 研究室HP
研究室HP