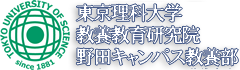2025年8月、科研費「研究活動スタート支援」により、ケニア・ホマベイ郡でスバ語のフィールドワークを実施しました。マンガノ島とルシンガ島に滞在し、漁師や農民と協力して日常会話や伝統知識を収集しました。これらは教育資源やAI学習ツールの基盤となるスバ語コーパスの構築に活用されます。
漁師は風や湖流、鳥の動きから天候を予測し、農民は自然の兆候で作付け時期を判断します。こうした知識は気候変動への適応や持続的資源利用に有益です。また、ケニアの母語教育政策(1〜3年生)を支援し、日本の初等教育モデルの理念にも学んでいます。
アバスバ共同体は舟大工や漁労で知られますが、現在スバ語は高齢層中心で、若年層はルオ語・スワヒリ語・英語を使用します。ユネスコは2003年にスバ語を消滅危機言語に指定しました。
本研究は東京理科大学の支援により進展しました。教養学部の助言に加え、伊高静教授と大学院生が自然言語処理の知見を提供しています。今後はデータのデジタル化・注釈付けを進め、小学校教材やAIアプリ開発を通じて言語継承を促します。本研究は、日本の技術と教育理念がケニア社会を支援し、文化保存と持続可能性に貢献できることを示しています。
Hesborn Ondiba
(野田キャンパス教養部 嘱託助教)