音のフーリエ解析(2009年度〜)
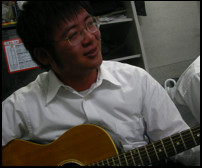
最後になりましたが、根気強く指導にあたって下さった満田節生先生、いろいろな相談にのってくださった中島さん、修士1年生の先輩方、そして気さくな同輩たちに感謝します。
東京理科大学理学部第一部物理学科 2008年度 満田研究室卒研生
中村健太郎 2009年3月末
-------
社団法人 私立大学情報教育協会「ファカルティ・デベロップメントとIT活用」2008の中のIT活用授業モデル(物理学)の記事の「V O D型テキストを活用した「音の分析」実験授業」の原稿(事例4の原稿)にありますように、2004年から一新した実験課題は、アンケート調査によると、「VOD 型テキスト自身の効用」については、数十秒程度の動画を効果的に多用したVOD テキストによる「手順説明」はわかりやすく効果的であると好意的に受け止められましたが、その反面、VOD 型テキスト中に織り込んだ「学習の誘導」については、やや評価点が低い傾向がありました。個別の自由記述を見ると、「一本の筋道を追い過ぎ(やらされている、せかされている感じ?)」、「時系列で縛っている(c.f.紙媒体のテキスト)」、「自身で考えながら実験を進めることのできる学生には窮屈(考えない学生にはOK?)」などがあり,VOD 型テキスト中に織り込んだ「学習の誘導」の難しさがあらわになりました。さらには、テキストの紙媒体がないことへの不満が大きく、学生の多くは、携帯できる紙媒体に結局プリントアウトしてしまったように「メディアの特性(紙.VS.画像)を考えたマテリアル構成」を考える必要性も見出されました。一般に、映像は体験させるには良いが蓄積保有するには向かないと言われていますが、「画像(音声)情報」と「文字情報」のすみ分けとそれらの携帯性を考える必要があります。
そのような状況で、2008年度に、中村健太郎君に、そのテキスト形式をそれまでのVOD(Video on Demand)形式から紙ベースに戻して、その実験課題をより厳選した改訂版を作成して頂きました。2009年3月末まで頑張ってくれた中村健太郎君に感謝します。
まだ見切り発車の設定課題もあり、より良い実験課題に高めてゆくためには、実験を実際に行った皆さんからのフィードバックが欠かせません。そこで、この「音のフーリエ解析」を終えた直後で印象の薄れないうちに、アンケートをお願いしています。実験/口頭発表/レポートと同様に、「学生実験課題」におけるプロセスとして、学生の皆さんからの忌憚のない意見を聞きたいと思いますので、この電子アンケートに協力をお願いします。このアンケート結果を分析しながら、2B学生実験(火曜コース/木曜コース)でこの実験題目を担当しているTA: 山田君、石井君および整備担当TA:吉冨君の協力のもと適時、修正を加えて行く予定です。
2009年3月 物理 満田
音の分析(2004年度〜2008年度)

まず、実験というのは本来、講義を聞いた上でその内容をもとにしながら行うのが非常に効果的です。しかし、今回は講義を聞いていない学生にも効果的な実験にするために、発見学的な実験を目指しました。発見学的な実験というのは、実験で目で見た事実をもとにして、その数学の必要性などを理解していくということです。このような実験にすることによって、フーリエ解析をゼロから理解できるのではないかと考えました。そして、現在のIT技術の進歩にともなった実験を目指しました。実験はすべてPCをベースにして行いました。またテキストは従来の紙のテキストをなくすことを考えました。紙のテキストを読んだだけでは、実験方法などが伝わりにくいため、実験方法の部分を動画で説明するVOD型テキストを導入し、実験の際にはモニターで動画を見ながら実験を進めていけるようにしました。これらの改良によって、物理学科の学生が効果的にフーリエ解析を理解できたら良いと思います。
最後になりましたが、根気強く指導にあたって下さった満田節生先生、ソフトの開発をしてくれた小泉修氏、実験装置などのことでサポートしてくれた橋本直哉氏に感謝します。
東京理科大学理学部第一部物理学科 2003年度 満田研究室卒研生
児玉綾子(こだまあやこ)2004年3月末
-------
『音声分析』は現在を遡ること約15年以上前に、既に退官された鈴木 清光 先生により、当時PCの出始めであったNEC pc9801にカノープスのAD & FFTボードを用いてデザインされた実験課題でした。しかしながらPCおよび音声取り込みの周辺機器の老朽化が激しく、2003年の前期には、ほぼ学生実験機材としての機能を失いつつある状態でした。2003年度の満田研 卒業研究生の児玉綾子さんに、卒業研究課題『教育工学的視点から見た学生実験課題/サイエンス夢工房/講義実験(フーリエ解析の定性的な理解のための「音声分析」実験開発)の一環として、旧 『音声分析』にあった『フーリエ変換の内容を音を用いて体感する』精神を引き継ぎ、新たに最新のPC(Apple iMac)を投入し、実験課題を一新して頂きました。
児玉綾子さんには、『学生実験課題』だけでなく、そこで導入した機材を生かし『サイエンス夢工房』、『講義実験』( FourierAnalysis 講義実験番外編(フーリエ解析で眺める「音」)Dec. 11 2003)にわたり全力投球していただきました。 児玉綾子さんに感謝します。
これらのマテリアルが物理学科の後進の学生のみなさんに長く活用されることを願っています。
2004年3月 物理 満田
https://www.rs.tus.ac.jp/mitsuda/onseibunnseki/index.htmll
問い合わせは理学部 物理 満田までメールでお願いします。
![]()