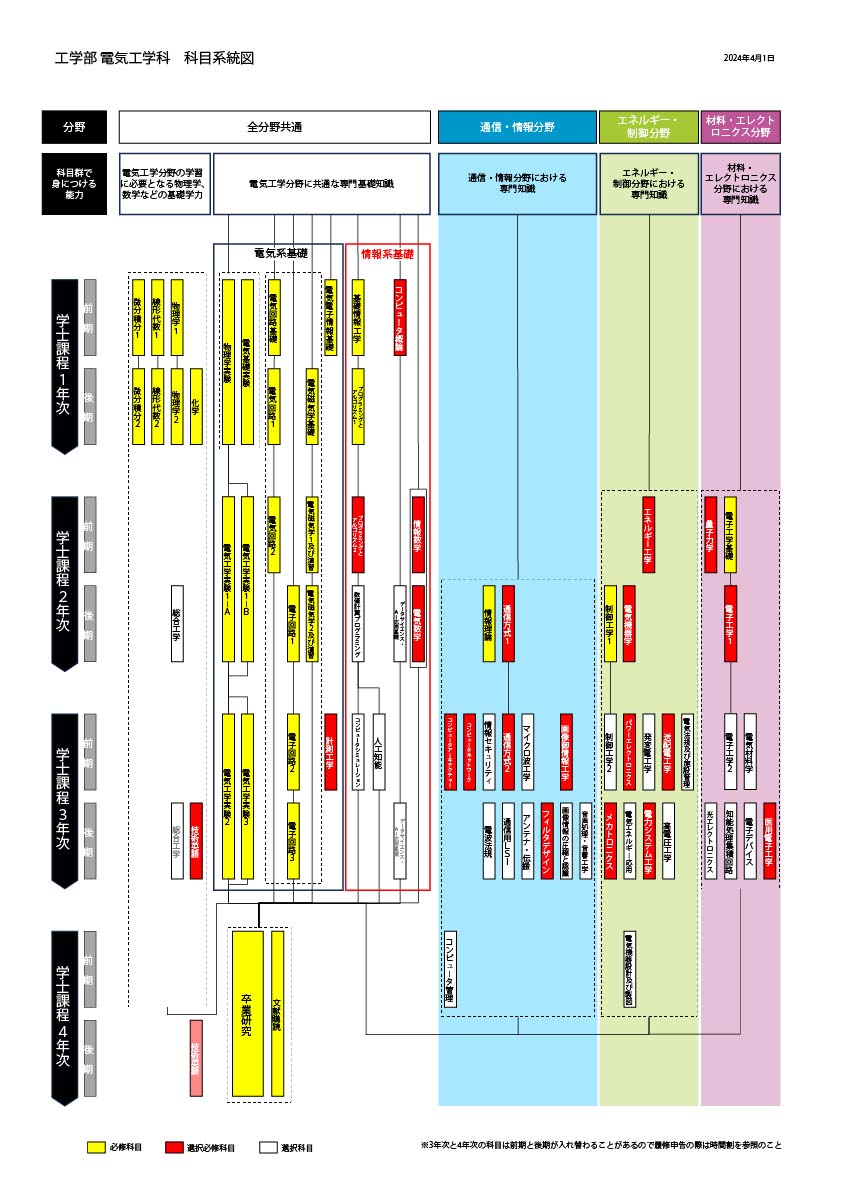資格について
当学科は下記の資格に関し,認定校になっています。
- 電気主任技術者
- 電気通信主任技術者
- 無線従事者:第一級陸上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士
電気主任技術者
電気工作物の工事、維持および運用に関する保安の監督を行うことのできる資格で、電気事業者と自家用電気工作物の設置者は、この資格を持つ者の中から主任技術者を選任しなければなりません。この資格には取り扱う電気工作物の規模(電圧)によって、すべての電気工作物が対象となる第1種を筆頭に3つの区分が定められており、第1種は大学で所定の科目を修得した後に5年、第2種は3年、第3種は1年の実務経験が必要です。
電気通信主任技術者
事業用電気通信設備の工事、維持および運用に関する監督を行うことのできる資格で、電気通信事業者はその事業用電気通信設備を直接に管理する事業場ごとに選任しなければなりません。資格者証には伝送交換主任技術者資格者証と線路主任技術者資格者証の2つがあります。所定の科目を修得すると、申請により試験科目のうち「電気通信システム」が免除されます。
無線従事者:
第一級陸上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士
電磁波を媒体とする通信、いわゆる無線通信に従事する人のことを無線従事者と呼びます。資格はアマチュア無線、陸上無線、航空無線、海上(特殊)無線、総合無線などに区分され、さらにそれぞれが3~4階級に細分化されています。そのため資格の種類は全部で23にのぼり、取得した資格によって活躍の場も実に多彩です。当電気工学科では、第一級陸上特殊無線技士および第三級海上特殊無線技士について、所定の科目を履修することにより資格が得られます。なお、無線従事者として一定の実務経験を積むと中学校の「職業」、高等学校の「工業」などの教員免許状を取得することもできます。